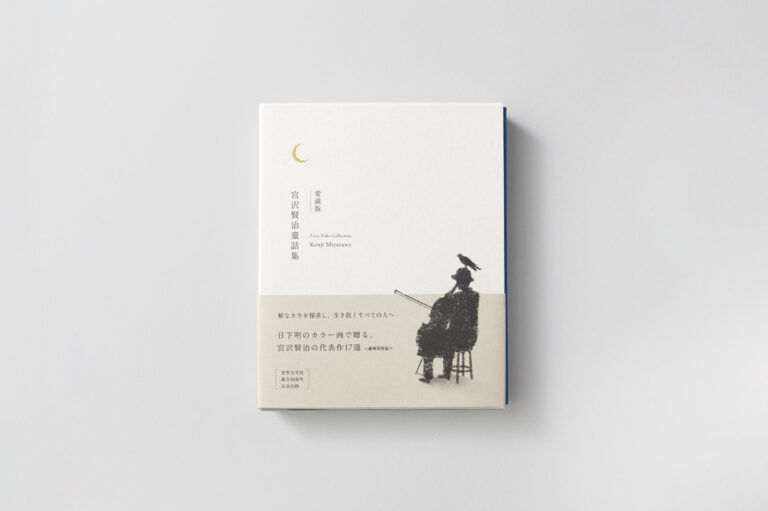木工作家としての歩み
1997年に初めて工芸の世界に足を踏み入れました。当時、韓国では赤ちゃん用のおもちゃに使用される素材や塗料の有害性が深刻な社会問題となっており、ちょうどその頃、私自身に第一子が誕生したのです。世界で最も安全で健康的なおもちゃを作りたいという想いから、木製のベビー用おもちゃを作り始めました。
当時、韓国には木で作られたおもちゃは殆どなかったので、私が作ったおもちゃはアトピー性皮膚炎を持つ子供たちに届けられるようになりました。次第に、私の木のおもちゃは“アトピーの子供専用のおもちゃ”として知られるようになっていったのです。
それと同時に、育児や家事に加えて、私と一緒に木工作業もしてくれていた妻の手首の状態が悪くなってしまい…次は、彼女のために「世界で一番軽い器を作ろう」と決意し、木と漆による実用性のある漆器を手がけるようになりました。

木との対話から生まれるかたち
木のおもちゃを制作するにあたり、私は国内外の様々な木材を扱いました。安全性を第一に考え、木材ごとの毒性についても徹底的に学びました。塗料による着色は行わず、木が本来持つ自然な色味を活かすことを大切にしています。
木は、乾燥の過程で自然に曲がったり、時には割れたりします。曲がることは自然の摂理として受け入れていますが、割れは作品の“痛み”となるので許しません。制作を始める際には、まず木目や年輪を見て、その木がどの方向に曲がろうとしていたのかを見極めます。そして、その日の湿度を確認し、加工する木の含水率と照らし合わせながら表現したいかたちに応じて厚みを調整しつつ削っていきます。乾燥方法も湿度と含水率のバランスによって決めています。自然乾燥なのか人工乾燥なのか、どの程度時間をかけるのか。最適な方法を選びます。この緻密な乾燥技術によって、木の個性を活かしながら自由な曲線を表現することができるのです。


漆における熱硬化との出会いと実験
従来の湿度による乾燥方法で仕上げた漆器に、初めて料理を盛りつけたときのことです。温かい料理や飲み物を入れると、器から強い漆の匂いがしたのです。特に熱を加えたとき、その匂いは一層強く感じました。なんとかこの問題を解決しようと、多くの文献を読み込み、漆に関する研究を重ねましたが、なかなか答えが見つかりませんでした。諦めかけていたある日、ある本の中で“漆を熱で硬化させると匂いが消える”という、数行の記述に出会ったのです。わずかな望みに賭けて実験を行ったところ、驚くべき結果が得られました。熱硬化させた漆器からは、まったく匂いがしなかったのです。
しかし問題は続きました。次の課題は、木を数百度の高温に耐えさせることでした。焼けてしまったり、割れてしまったり。またしても試練の連続でした。それでも諦めずに研究を続け、今では約90%の成功率で熱硬化による漆器を完成させることができています。
木の年輪は自然の記憶そのものです。年輪を活かしながら水分量を調整し、器としての造形を仕上げていきます。年輪の美しさがそのまま器に残るよう、漆は薄く幾重にも塗り重ねて仕上げます。木で器を作る文化は世界中にありますが、漆がなければ木は主材料として定着しませんでした。実用的な側面から漆の存在が不可欠だったのです。以前ドキュメンタリー番組で、1000年以上経っても分解されない陶磁器の映像を目にしました。それに比べ、漆塗りの木器は自然に還る素材です。約一年で分解され土に還っていきます。自然の記録を宿した素材を用い、自然のサイクルに戻っていく器。私のもの作りの根底にはそんな自然との対話があります。


自然からの表現と感性を宿す器
私が小学3年生のとき、釜山から韓国北部の江原道・束草(ソクチョ)へ引っ越しました。日本で例えるなら、鹿児島から札幌へ移動するような感覚です。束草には韓国を代表する国立公園・雪嶽山(ソラクサン)があり、その山から見える蔚山岩(ウルサンバウィ)という巨大な岩があります。街の中にはふたつの湖があり、雪嶽山と湖に囲まれるように都市が存在しています。釜山では一度も見たことがなかった大雪、海の大きな波、美しい紅葉に包まれた山々。束草の自然を私は心から愛し、その豊かさを日々楽しみました。結婚を機に、現在拠点を置く韓国の工業都市・蔚山(ウルサン)に移ることになり、あらためて束草の自然の尊さに思いを馳せました。私の作品には、そうした束草の風景が深く刻まれています。山の稜線や湖畔のゆるやかな曲線、冬の晴れわたる青い空、雪嶽山の緑と青を混ぜたような深い色、夏の白い雲、街をすべて白く染める雪、海辺から見た夕焼けの赤や黄、そして光に照らされなかった雲の灰色。これらすべてを、木の年輪の線や漆の色を通して表現しています。


私が手がけているのは、伝統的な器である箱、皿、茶碗です。それらは韓国における生活の歴史そのものだと思っています。韓国の工芸は、土器や陶器から始まり、青磁、粉青、白磁という磁器の歴史を歩んできました。色や素材が異なっていても、形を見ればその時代の暮らしが映し出されています。
私がよく手がけるハムジという器は、腰がなく平たく、どこか謙虚な佇まいをしています。壺や瓶は口が小さく中が見えづらいのに対して、ハムジは入り口と胴体の幅がほぼ同じで、中がすべて見渡せます。つまり、隠し事がない器なのです。貴賤の区別もなく、誰でも使える素朴な美しさがあります。
制作における哲学と革新
制作の根底には、李禹煥(リ・ウファン)氏の作品《関係項(Relatum)》から受けた深い影響があるのですが、彼の素材そのものの存在を尊重し、作品と人、そして空間との関係性を重視する姿勢に心を動かされました。この時から、必要以上の機能や装飾をそぎ落とし、自然と人為のバランスを大切にする制作へと進んでいきました。
私は、2023年に開際された〈Seoul Yoolizzy Craft Award〉において、初代大賞を受賞しました。韓国の工芸において、現代工芸はファインアート化するあまり実用性を失いがちであり、対して伝統工芸は実用性にとどまり、時代から取り残されているように感じていました。だからこそ、工芸には新たな基準が必要だと考えていました。そのような中で、作品を通じて芸術性と実用性の両立が評価されたことは、嬉しい出来事でした。

私にとって、芸術とは感性を記録し、それを通して想いを伝えること。そして工芸は、実用性という土台の上に芸術的な感性を重ね表現することだと考えています。工芸において実用性は欠かせない要素ですが、もっとも大切なことは作品に込められた感性を届けることです。私の感性の源は“自然”にあります。ただ、私が伝えたいのは自然そのものではなく、自然という存在を通して人々が心で自由に感じとることが大切で、そこに私の願いがあります。
今回、日本という漆器において豊かな伝統を持つ国で個展を開催できることは、私にとって大きな喜びであり、同時に大きな挑戦でもあります。作品に込めた意図や表現、そして想いを、ぜひ感じ取っていただけたら嬉しいです。そして何より、熱い飲み物や料理を実際に盛り付け、使い手として器の手触りや実用性を体感してみてください。
HIN / Arts &Scienceでは、5月9日(金)から東京で、5月23(金)より京都で、彼の日本初となる個展を開催いたします。静かな情熱と、素材への深い敬意が込められた大小様々な作品群をぜひご覧ください。
PROFILE
1969年、韓国生まれ。豊かな自然の中で育つ。1997年、我が子のために木製玩具を制作したことをきっかけに木工の道へと進む。自然から着想を得ながら、日常使いの器から大規模な作品に至るまで、幅広い創作活動を展開している。主に地元の木材を用い、韓国の伝統的な漆塗り技法に独自の高温硬化技法を融合させた、機能性と耐久性を兼ね備えた器を制作。2020年には〈ロエベ ファンデーション クラフト プライズ〉のファイナリストに選出。国際的にも高い評価を受けている。